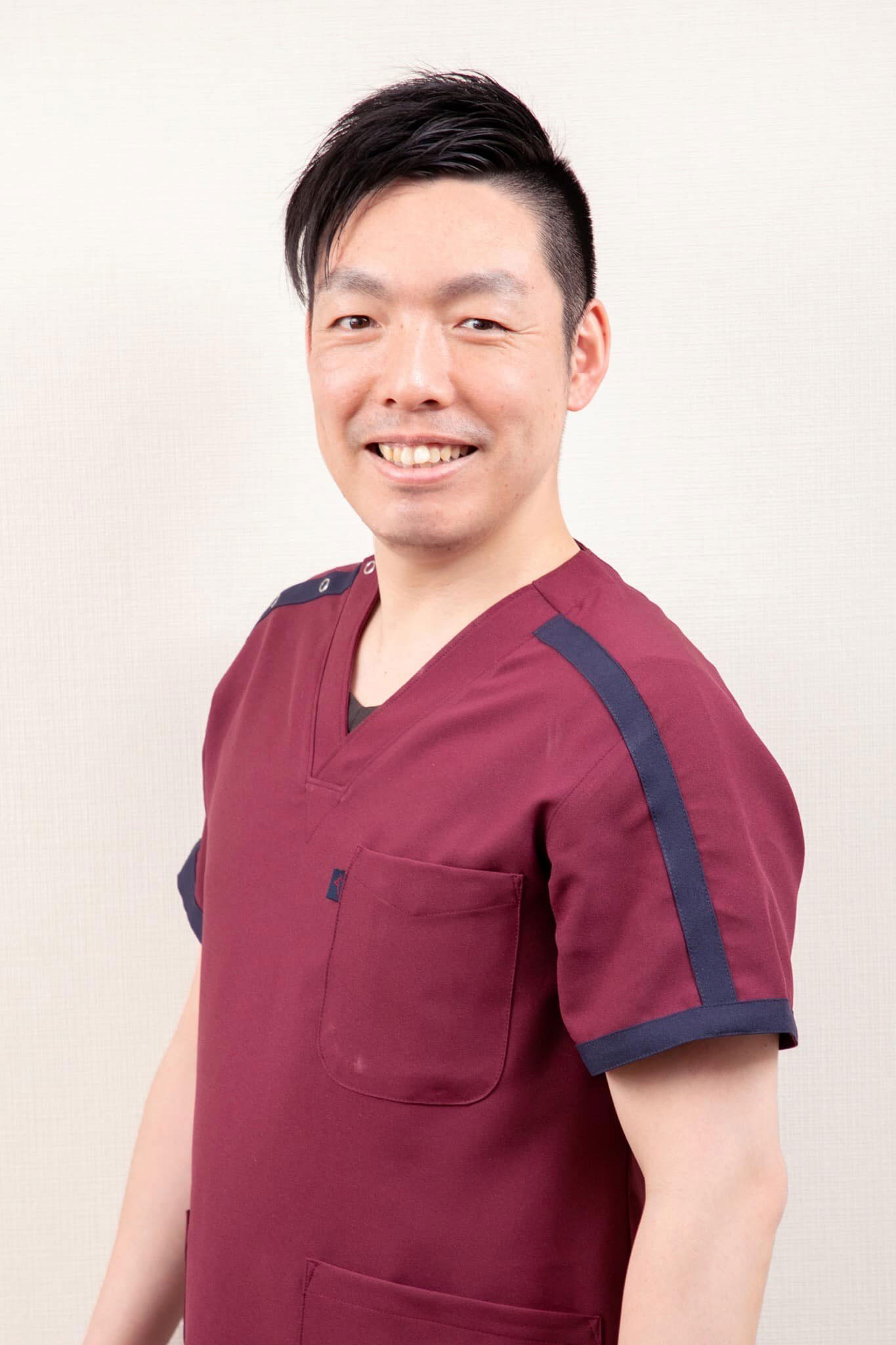シーバー病なんですがインソールは作った方が良いですか?│正しい使い方と注意点

シーバー病に悩む方たちから、よくいただく相談内容です。
一般的には、整形外科や整骨院でもお勧めされることが多いんですけどね。
思ってたのと違う!とならないように、正しくインソールを活用するヒントにしてください!
シーバー病とインソール

シーバー病(踵骨骨端炎)は、成長期の子ども・思春期の若者に起こりやすい、踵の後方・底部付近の痛みを特徴とする成長軟骨部の障害です。
ランニングやジャンプ、踏み込み動作など足への衝撃が強くかかるスポーツ活動を行っている子ほど発症リスクが高いと言われます。
痛みが出るために、競技の継続が難しくなったり、安静を強いられたりするケースも少なくありません。
こうした症状が出たとき、多くの人が「痛みを軽減する」「早く運動を続けたい」という思いから、サポート具(例えばテーピングやインソールなど)に頼りたくなります。
実際に通っている整骨院やスポーツ用品店から「インソールを作るのがお勧めですよ!」と言われたというケースも少なくありません。そして、そこから「シーバー病にはインソールは使った方が良いのか?」という相談もたくさんいただきます。
しかし残念ながら、これには「万能な正解」があるわけではないんです。
目的や個人の状態によって使う・使わないの判断が変わります。
シーバー病でインソールを使用する場合は、「目的をはっきりさせたうえで使うなら意味を持つが、盲目的に使うと逆効果になり得る道具」であるんです。
優れた道具ほど、使い方を間違えれば、逆効果も大きくなってしまうのです…
インソールを使う「メリット」と「限界・注意点」
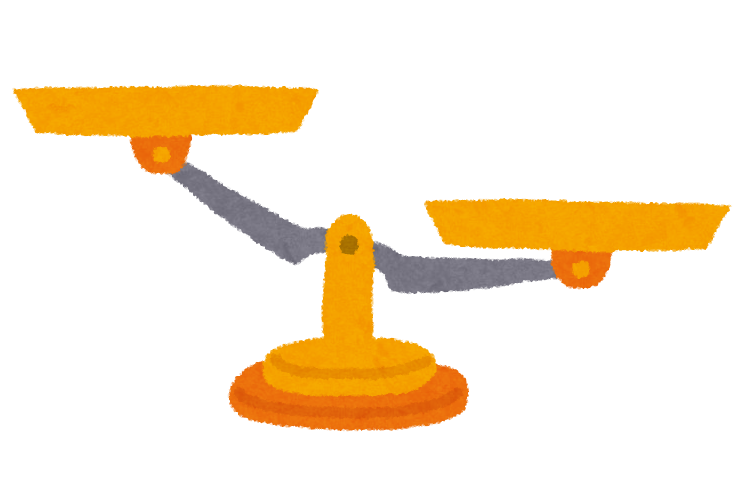
まず、インソール(サポート用中敷き)を作成することのメリットから見てみましょう。
適切な形状・硬さ・補正設計を備えたインソールは、踵部への衝撃を分散したり、足底のアーチや荷重線(足の重心のかかる線)を整えることで、踵にかかる余剰な負荷を減らします。
特に、扁平足傾向・内反/外反などのアライメント異常がある人では、脚の使い方や足関節・膝関節との連動性が崩れていることが多いため、それを補正する意味でのインソールは理にかなっていることもあります。
しかし、次のような限界や注意点を無視できるものではありません。
・痛みを“治す”ものではない
インソールはあくまで補助具であり、痛みを根本から消す魔法の道具ではありません。
「インソールを使っていたらいつの間にかシーバー病ではなくなっていた」というものではないんです。あくまで、「シーバー病になる要因を補正するもの」「踵に負担がかかりにくくなるもの」でしかないんです。
インソールで痛みが軽くなるのは、あくまで衝撃緩和やアライメントの補正を通じてです。根本的改善には、使い方(動作・フォーム)、筋肉の柔軟性・バランス、適切なトレーニング調整や休息などを調整する必要があります。
・過度な補正設計は逆効果になり得る
「これで完璧に補正してくれる」と思って過剰な補正力を持たせたインソールを使うと、足や脚の適応機能を奪ってしまい、自力でバランスを取る筋肉・関節への刺激を減らすことがあります。
そうすると、インソールがないと運動できない体になってしまうことにもなります。そうなるとインソールを外したときに再び痛みがぶり返すリスクが出ます。道具への過度な依存が症状を長引かせる要因になるリスクもあります。
身体的な依存というだけでなく、「インソールがないと不安になる」といった精神的な依存にも繋がる可能性もあります。
・個人差と設計精度の問題
インソールの効果は、設計の精度(形状、素材、硬さ、補正要素)と、個人の足・脚の構造や動作パターンとのマッチングに左右されます。安価な既製インソールでは、自分の足型・動作特性に合わないことも多く、かえって不適切な荷重分布を生む場合もあります。また、痛みの段階(炎症期/回復期)によって求められるサポート特性も異なるため、時期に合わせて使えるインソール設計が必要なこともあります。
オーダーのインソールでは、補正するだけなのか、インソールを卒業できるように体を教育していくものなのか、という作成者の方向性での違いもあります。自分自身の意図と作成者の意図のすり合わせは必須になります。
・使用期限とコストの問題
インソールは体が受ける衝撃を肩代わりしてくれるものでもあります。その分、インソールへのダメージも大きく、使用頻度に合わせて消耗していきます。
オーダーメイドで作成したインソールの場合、半年~1年で作り変えを勧められることが多いです。既成インソールだと安価ではありますが、オーダーメイドのインソールだと1万円~3万円ほどになるので、インソールに頼るとコストがかさんでしまうケースもあります。
メリットもあるのですが、インソールで出来る限界と注意点は理解しておくことが大切です。
インソールは作るべきか?その条件と心構え

結論から言うなら、「絶対にインソールを作らねばならない」のではなく、「状況次第で有用な道具になり得る」という立ち位置が適切です。
「目的がはっきりしており、道具を使う意味と限界を理解したうえで使う」ことが、道具を使ううえでの前提条件となります。
具体的には、痛みをただ抑えたいだけの目的でむやみにインソールを作るのではなく、まずは痛みの原因(使い方、柔軟性・可動域の制限、強い負荷動作、休息・負荷配分の不適切さなど)を見極め、これらに手を入れることが先決です。
そのうえで、アライメント異常や荷重不均衡が見られ、かつ改善の補助が欲しいと判断できれば、インソール作成は選択肢として有効です。
ただし、次のような心構えを持つことが重要です。
道具は“助け”であって“解決”ではない
インソールだけで痛みが消えるものではなく、適切な使い方・併用治療が不可欠です。
過信・依存を避ける
インソールがあるからといって、無理をして高負荷の運動を繰り返すと逆に悪化するリスクがあります。道具に頼り過ぎないように注意をしてください。
定期的な見直しを行う
成長期であれば足型も変わることがあります。また消耗したインソールを入れていても意味がないどころか悪化するケースもあります。インソール設計や補正要素の見直しも視野に入れて運用すべきです。
専門家の判断を仰ぐ
足部やスポーツ障害に詳しい整形外科医、理学療法士、柔道整復師、トレーナーなどの専門家と相談しながら、インソール設計や運用方針を決めるのが安全・効果的です。
最終的には、シーバー病になっているかどうかだけで「インソール作るべきか?」と即断するのではなく、「自分の足・脚の状態」「痛みの程度・段階」「動作やフォームの改善余地」「併用可能な治療・トレーニング体制」「目標や目的」などを総合的に見て判断していくべきです。
いずれにせよ大事なのは、インソールで治るものではないので、シーバー病を治すためには適切な対処を取らないといけないということです。
出来る事なら、施術を受けるだけでなく、シーバー病になってしまった体の使い方を見直していくことを強くお勧めします。
実際に、当院では、走り方などの体の使い方を変えるオンラインでのサポートを行っていますが、それだけで「シーバー病が良くなった」という子たちはたくさんいます。
施術を受けても治らない、繰り返すというので悩んでいるなら『自分で治す』という選択肢も考えていただければと思います。
↓↓↓
シーバー病について、Youtubeでもご説明しています。