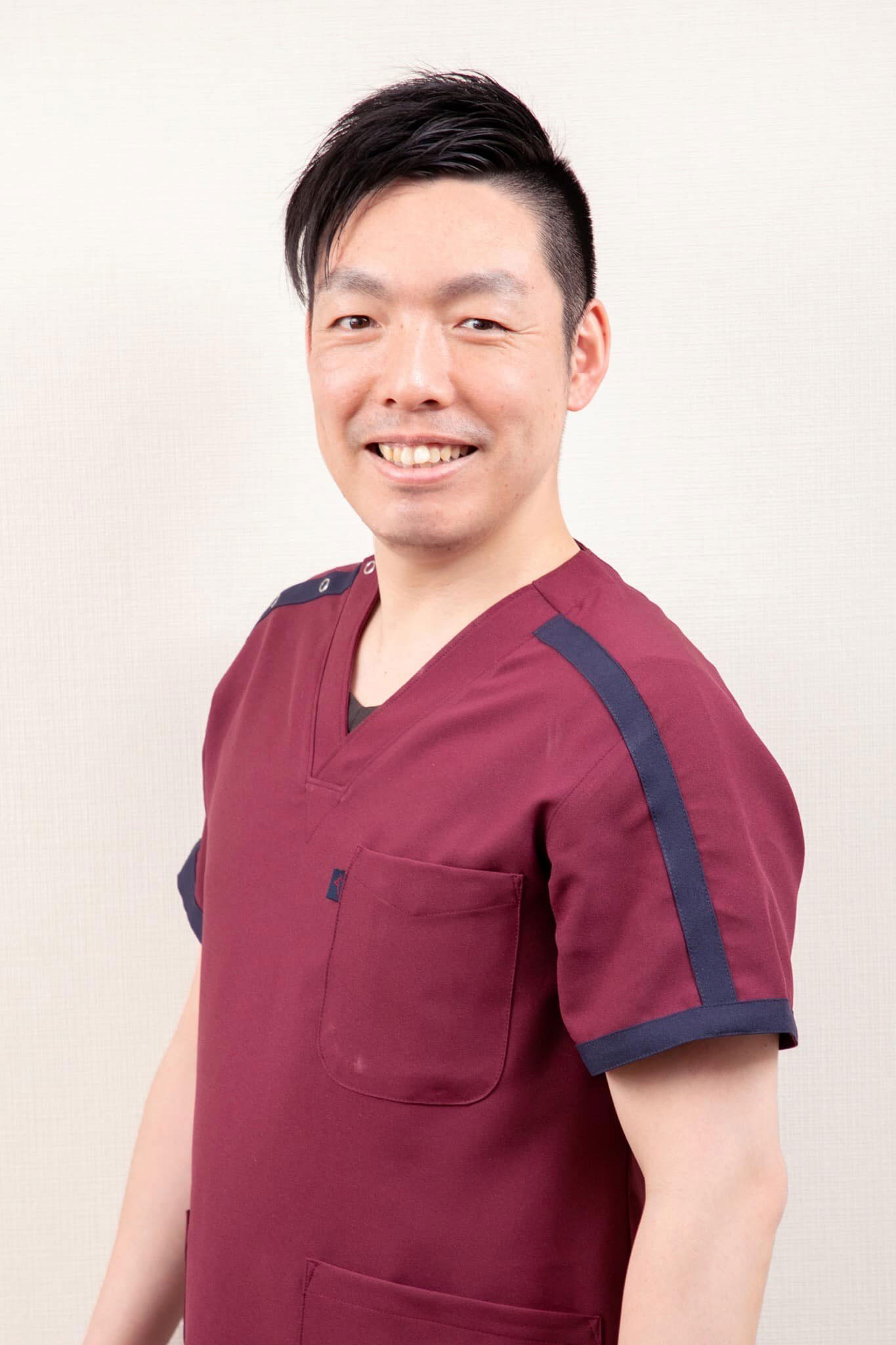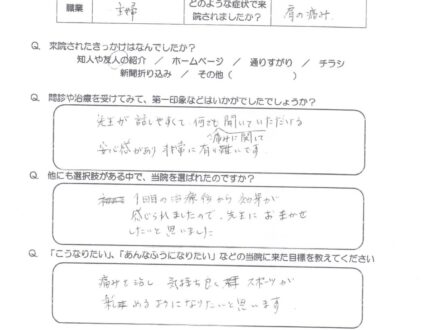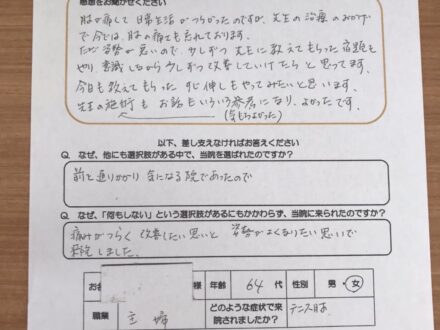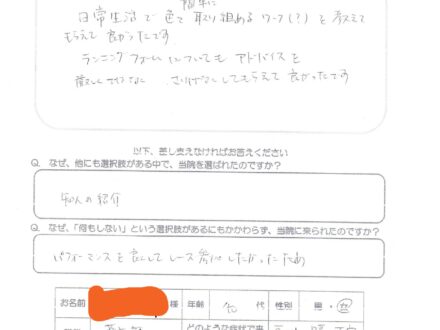チームの子たちのケガを減らしたい!│ケガ予防とパフォーマンスアップの体の使い方講習会│朱六FC

先日、朱六FCの監督さんからご連絡をいただきました。
「チームの子たちのケガを減らすのにはどうすれば良いかな?」
「膝や腰を痛めてる子たちがいるんやけどどうすれば良いだろう…」
チーム運営をしている方にとってはよくあるお悩みだと思います。
実際に、今までもそういったご相談をいただくこともたくさんありました。
もし、お子さんの所属しているチーム、運営しているチームで、
『ケガを減らしたい』、『効率的にうまくさせてあげたい』というお悩みを持っておられるならお気軽にご相談いただければと思います。
・ケガを減らすには、ケガを知ることから

『己を知り敵を知れば百戦危うからず』
中国の兵法書『孫子』の一節で、「自分自身のことをよく理解し、敵のことをよく知っていれば、何度戦っても負けることはない」という意味の言葉です。
ケガについても同じことが言えます。
まずは自分のことを知る。
・自分の体を正しく把握する
・自分の体を思い通りに動かせる
そしてケガのことを知る。
・なぜケガが起こるのか?
・どうすれば防げるのか?
文字に起こすとかなりシンプルなんですが、これがめちゃくちゃ大事なことです!
知ってるのか、知らないのか、この二つの違いが大きな差になってきます。
なぜ、ケガが起こるのか?
その時に、自分の体には何が起こっているのか?
ということが分かっていれば十分にケガは防ぐことができるのです。
・ケガをするほど上手くなれる!

『チャンスはピンチの顔をしてやってくる』
イギリスの元首相チャーチルの言葉で、一見すると困難に見える状況が、実はチャンスである場合がある、という意味の言葉です。
『ピンチはチャンス』
元陸軍軍人で実業家だった大橋武夫氏が、孫子の兵法を基に、一般の人にも分かりやすく表現した言葉です。
このように、一見「ちょっとやばいな…」という状況にこそ、大きく飛躍するためのヒントが隠れているというものです。
だからこそ…
ケガはするほど上手くなれる!んです。
アクシデントなどで一回の衝撃でケガをするようなもの以外のケガ…
使い痛み・オーバーワーク、蓄積によるケガについては、実はうまくなるチャンスなんです!
例えば、成長期によくあるオスグッド。
膝が痛くなるスポーツ障害ですが、スポーツをしている中で膝に負担がかかり続けていた結果です。
同じく、成長期に多いシーバー病。
これは踵が痛くなるスポーツ障害なんですが、踵に負担がかかり続けていたという結果でしかありません。
激しくスポーツをしていた経験がある人の30~40%の人が罹患していると言われている腰椎分離症。
腰に負担がかかるような体の使い方をしているから、腰の骨が分離(疲労骨折)してしまったんです。
このように、痛みが出るということは、体の一部分に負担が集中してしまった結果なのです。
ではその集中してしまった負担を他の部分に分散できれば…?
負担は少なくできると思いませんか?
逆に言うと、、、
今まで使えていなかった部分を使えるようになるということ。
オスグッドなら膝、シーバー病なら踵、腰椎分離症なら腰に負担がかかっていたということ。
それぞれ、もっと大きくて頑丈な関節や筋肉が使えるようになると、
発揮できるエネルギーも大きくなるんです!
・体の使い方を変えるという痛みの治し方

ケガのことを知る、自分のことを知ることで、『なぜケガをしたのか?』ということを解決すれば、
ケガは最短で治っていきますし、再発も防げます。
ケガの理由がなくなるわけですからね。
痛みを治そうとして、治療や施術を受ける事よりも、
痛みの理由を解決する方が、実は早期復帰・再発予防が同時に得られるのです。
そして、ここで重要で残念なお話なのですが…
痛みの理由を解決する、ということは、
お医者さんやリハビリの先生、整骨院の先生、トレーナーができるものではないのです。
プロとはいえ、他人の体に干渉できるのは、対症療法でしかないんです。
ということは…
自分自身でしか解決できない!
ということなんです。
体の使い方は自分自身でしか変えることができません。
膝や踵、腰など、一か所に負担が集中するような体の使い方をしていたのを、
全身を連動させるような体の使い方ができるようになるのが超重要なんです!
・まとめ
自分を知ること
ケガを知ること
そして、
正しく対処ができれば、
ケガをするほど上手くなれる!
そのためにも、
体の使い方を変えることで自分で解決できることができる!
ということを知ってるか、知らないかという小さな違いは、
今後のスポーツ人生において大きな差になってきます。
ケガに怯えることなく、不安や悩みを抱えることもなく、
思いっきりスポーツを楽しんでもらえたらと思います。
部活動やクラブチームにも
ご依頼をいただければ、
・ケガ予防
・パフォーマンスアップ
・身体操作、体の使い方
などについての講習会も行っています!
ご興味のある方はお気軽にご相談いただければと思います。