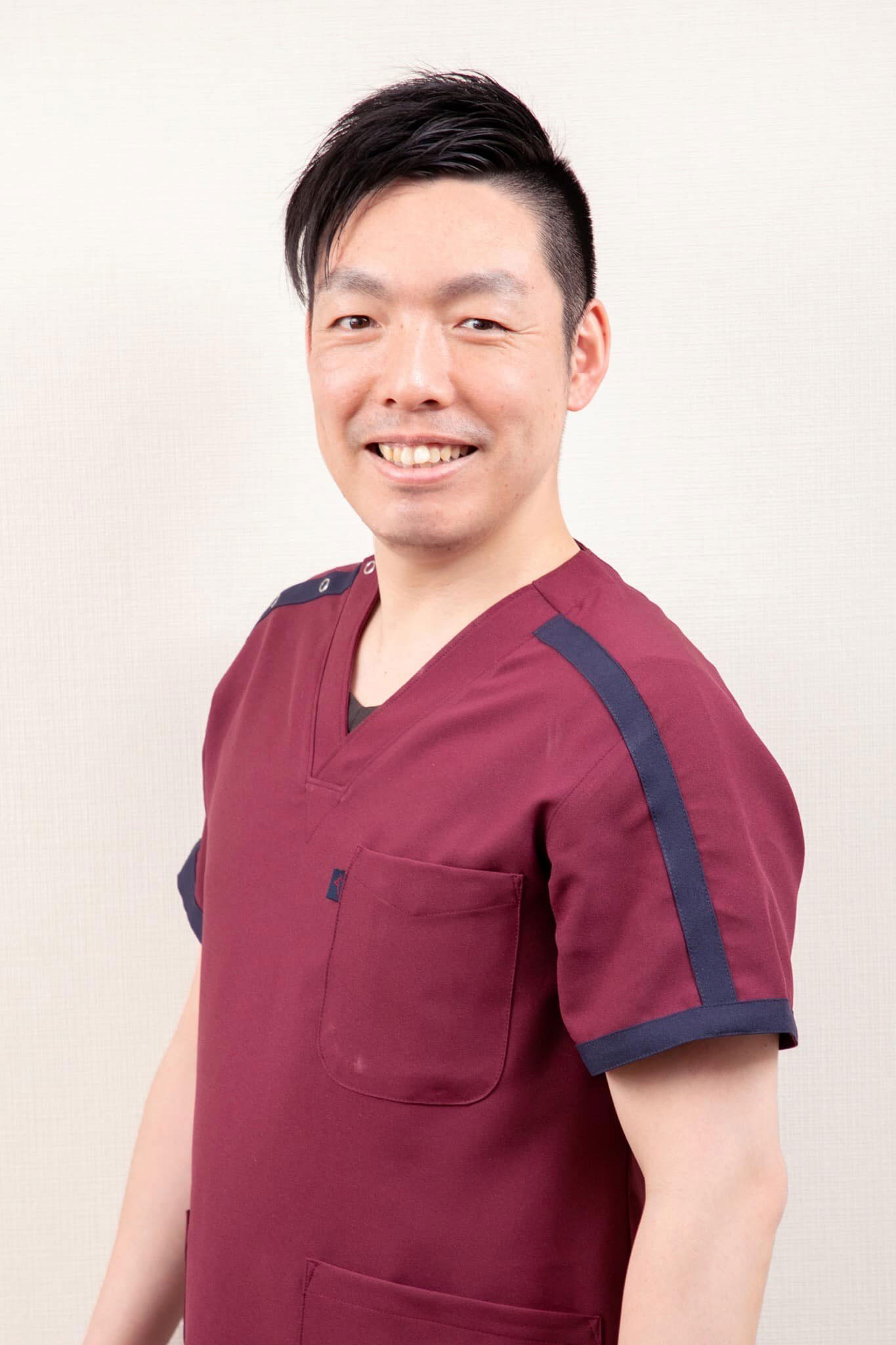その指導、本当に大丈夫? ~部活動に潜む「時代遅れの常識」を考える~

青春の1ページとして、多くの人の記憶に刻まれる部活動。仲間と汗を流し、目標に向かって努力する日々は、技術の向上だけでなく、人間的な成長を促すかけがえのない時間です。
熱心に生徒と向き合い、その成長を力強くサポートしてくださる素晴らしい指導者がたくさんいることも、私たちは知っています。
しかし、その一方で、指導者の言動に「モヤモヤする」という声が、生徒や保護者の間から聞こえてくるのも事実です。それは、単なる厳しい指導という言葉では片付けられない、子どもたちの心身を危険に晒しかねない問題です。
本記事では、一部の部活動の現場で見られる、時代遅れとも言える指導法に焦点を当てます。実際に患者さんから聞いた話を基に構成しています。
これは特定の個人を非難するためではなく、すべての子どもたちが安全な環境でスポーツに打ち込める未来のために、指導者、保護者、そして社会全体で考えるべきテーマだからです。決して全ての指導者がそうだというわけではありません。しかし、今もなお存在する「悪しき慣習」から、私たちの大切な子どもたちを守るために、一度立ち止まって考えてみたいのです。
目次
<strong>「根性論」が奪うもの ~健康と安全が脅かされる現場~</strong>

「昔はこれくらい当たり前だった」「精神力が足りないからだ」――。こうした言葉を盾に、科学的根拠を無視した指導がまかり通っている現場があります。その最たる例が、生徒の健康と安全を軽視する風潮です。
例えば、真夏の蒸し暑い体育館。生徒が頭痛を訴え、見学を申し出たところ、「いつまでサボっているんだ!」と怒鳴られる。これは、熱中症の初期症状を「怠け」と断じているに等しく、命の危険に直結する、極めて問題のある言動です。
また、「練習中は水を飲むな」という、もはや都市伝説レベルの指導が、いまだに一部で生き残っているというから驚きです。さらに、学校の自動販売機や購買での水分購入を禁じ、「家から持ってきたもの以外は飲むな」と強制するケースもありました。これでは、必要な水分量を確保できないばかりか、生徒は重い荷物を毎日運ぶことになり、身体的な負担が増し、かえってパフォーマンスの低下や怪我のリスクを高めてしまいます。
用具の問題も深刻です。「チームの一体感」を理由に、全員に同じモデルの靴を強制する部活があります。見た目の統一感は美しいかもしれませんが、一人ひとり足の形は全く異なります。合わない靴を履き続けることは、外反母趾や足底筋膜炎といった怪我を誘発するだけでなく、本来の力を発揮することも妨げます。これは、勝利を目指す上でも非合理的な選択と言わざるを得ません。
これらの問題の根底にあるのは、「気合いで乗り越えろ」という前時代的な根性論です。しかし、現代のスポーツ科学は、適切な休息、水分補給、そして個々に合った用具こそが、選手の能力を最大限に引き出し、安全を守るために不可欠であると証明しています。指導者が自身の経験則だけに固執し、学ぶことを怠れば、それは指導ではなく、単なる危険行為になってしまうのです。
<strong>怪我は「自己責任」なのか? ~指導者に問われる知識と責任~</strong>
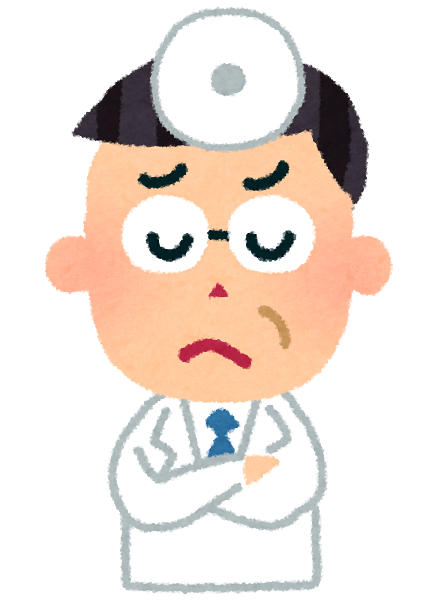
スポーツに怪我はつきもの、という言葉があります。しかし、その怪我への対応にこそ、指導者の資質が問われます。残念ながら、生徒の痛みのサインを軽視し、さらなる悪化を招くような指導も後を絶ちません。
「ストレッチで痛みを感じる」と生徒が訴えても、「痛いのを我慢しないと他の怪我をする」と、痛みをこらえさせて強行させる。これは、身体が発している危険信号を無視する行為であり、筋肉や靭帯の損傷を悪化させるだけです。
治療の観点からも全く意味がありません。
痛みを訴える生徒に対して、「まだできる!頑張れ!」と精神論で追い込む。
サポーターやテーピングで患部を保護しているにもかかわらず、「そんなものに頼るな」と外させる。
これらは、生徒の身体を守るどころか、積極的に破壊しているに等しい行為です。
さらに憂慮すべきは、指導者の責任転嫁の姿勢です。
チームの半数以上がオーバーユース(使いすぎ)による怪我を抱えているという異常事態にもかかわらず、「お前たちが体幹が弱いからだ」と選手個人のせいにする。
もし本当に選手の体幹が弱いのであれば、それこそが指導者が取り組むべき課題のはずです。選手のコンディションを把握せず、過度な練習を課し続けた結果を棚に上げ、責任を選手に押し付けるのは、指導者としてあまりに無責任ではないでしょうか。
治療のために練習を休んで治療に行くことを認めず、「見学」を強制するケースもあります。もちろん、見学から学べることもありますが、最優先されるべきは怪我の治療と回復です。回復を遅らせてまで練習場所に縛り付けることに、どれほどの教育的価値があるというのでしょうか。
「大切な子どもたちを預かっている」という意識があれば、まずは専門医の診断を仰がせ、一日も早い回復をサポートするのが指導者の務めです。
怪我は自己責任ではありません。
その多くは、不適切なトレーニング計画や、指導者の知識不足によって引き起こされる「指導者災害」なのです。
<strong>誰のためのルール? ~目的を見失った指導の果てに~</strong>

部活動には、規律を保つために様々なルールが存在します。しかし、中にはその目的が不明瞭で、単に指導者の価値観を押し付けるためだけの、理不尽なルールも見受けられます。
代表的なのが、競技に何ら関係のない「髪型」の強制です。「スポーツマンらしく」という曖昧な理由で、坊主やショートカットを強要する。これは、多様性が尊重される現代において、個人の自由を著しく侵害する時代錯誤なルールと言えるでしょう。生徒の主体性や個性を尊重する姿勢が、指導者には求められています。
また、練習時間の問題も深刻です。あらかじめ決められていた終了時間を、指導者の都合で「あと30分延長!」などと安易に覆す。
生徒の中には、その後に塾や家庭の用事を控えている子もいるでしょう。指導者は生徒に「時間を守れ」「約束を守れ」と説く一方で、自分自身が平気で約束を破っている。
この矛盾した態度では、生徒からの信頼を得ることはできません。計画性のない練習は、選手の集中力を削ぎ、疲労を蓄積させ、結果的に怪我のリスクを高めるだけです。
結果が出れば「俺の指導のおかげ」、結果が出なければ「あいつはそれまでの選手だった」。
このような態度を取る指導者はいないと信じたいですが、そう見えてしまう言動があるのも事実です。指導者は、生徒の人生の一時期を預かる、非常に重い責任を負っています。その自覚を忘れ、自分の存在価値を確認するため、あるいは自己満足のために生徒を支配するようなことがあっては、断じてなりません。
<strong>未来のために、今こそ声をあげよう</strong>

ここまで、部活動における問題のある指導について見てきました。繰り返しますが、これは一部の事例であり、多くの指導者は日々研鑽を積み、生徒一人ひとりと真摯に向き合っています。しかし、その一部の「時代遅れの指導」によって、心身に深い傷を負い、大好きだったはずのスポーツから離れてしまう子どもたちがいる現実から、私たちは目を背けてはなりません。
指導者の方々には、自身の経験則だけを信じるのではなく、常にスポーツ医科学やコーチングに関する最新の知識を学び続けてほしいと切に願います。もしくは、トレーナーなどの相談できる人とつながりを持っていただければと思います。
過去の成功体験が、今の子どもたちにも通用するとは限りません。時代とともに、子どもたちの体格も、考え方も、そしてスポーツを取り巻く環境も変化しているのです。
そして、保護者や生徒自身も、おかしいと感じたことには勇気を持って声を上げることが重要です。指導者と対立することを恐れる気持ちは分かりますが、子どもの安全と未来以上に大切なものはありません。学校や教育委員会など、相談できる窓口は必ずあります。
部活動が、すべての子どもたちにとって、心身ともに健やかに成長できる、かけがえのない場所であり続けるために。古い価値観や悪しき慣習をアップデートし、誰もが安心して情熱を注げる環境を、社会全体で築いていく時が来ています。