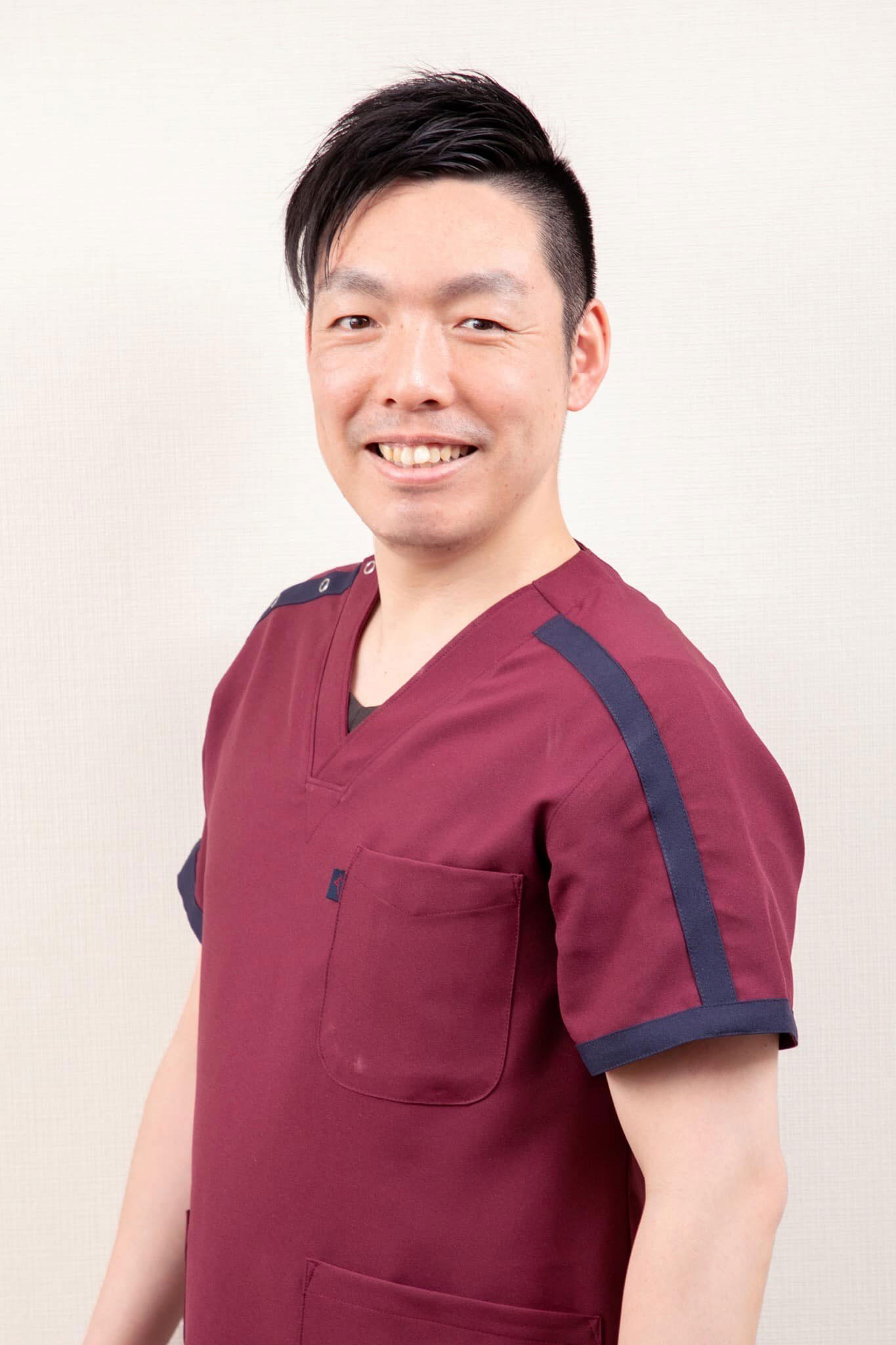京都両洋高校サッカー部での講習会で、改めて身体操作の大切さを感じた話
- 身体操作「ケガをしない体の使い方」の講習会

先日、京都両洋高校のサッカー部に「ケガをしない体の使い方」の講習会に行ってきました!
本日で2回目のご訪問になるのですが、きっかけは南茨木にある「たくみ整骨院」の伊藤先生からのご縁でした。
伊藤先生のところに、両洋高校のサッカー部から「体の使い方」の講習会の依頼があり、京都ということとサッカー経験者ということでお声をかけていただきご一緒させていただきました。
伊藤先生は「足が速くなる走り方」の講習をされるとのことで、
初めは、一緒に行って、「話聞いてるだけでいいか~」とか余裕ぶっこいてましたが、、、
「せっかくやし1時間ほどケガをしない体の使い方について講習して!」
とのこと…。
おふぅ…笑
ということで前回お邪魔した時は、「ケガをしない体の使い方」ということで、
姿勢や立ち方など基本的なことをお伝えさせていただきました。
そして2か月後の今回は、伊藤先生は「足が速くなる走り方パート2」と「止まり方」の講習を。
私はグロインペイン(サッカー選手に多い股関節の痛み)が長引いている選手がいるとのことで、
「痛くならない蹴り方」の講習を予定していました。
その後、「GK(ゴールキーパー)のパフォーマンスアップ」の講習も追加になりました。
- 身体操作の答えは1つではない

身体操作や体の使い方って、いろいろなところでちょくちょく聞くようになりました。
最近だと、「AIを使った動作分析」とかって整骨院に営業に来られたりもしています。笑
動作分析もすごく大切なんです。これは間違いありません。
でもその上で、それだけだと不十分でもあるんです。
どういうことかというと、、、
大学などの研究機関で行われている、動作分析って3Dモーションキャプチャーのような装置を使ってデータを採るということをしていくと、
『どのような動きをしているか』
ということが分かるようになります。
で、その時のパフォーマンスと繋げて、
『Aのような動きをしている時はパフォーマンスが高い』
という分析ができます。
そこから、『Aのような動きをしましょう!』となります。
高いパフォーマンスが出せるので当然ですよね。
でもここに落とし穴があるんです。
人間の構造上、『この動き方が正解だ!』みたいなことも言えたりするんです。
ですが、実際にはトップレベルの選手たちってみんなフォームがバラバラ…
それぞれ、自分の良さや特徴を活かした結果の記録だったりパフォーマンスだったりするのです。
ということは、『動き』から作ろうとすると、どんどん自分の良さや特徴から離れていくリスクもあるんです。
- 動きは結果、そこに繋げるのは自身の身体感覚

動作分析をした時の『A』という動きはあくまで外(第3者)からの視点であって、
自分自身はどのような感覚で『A』という動きになっていたかは別問題なんです。
例えば、無意識にその動きをしていた場合、
『A』という動きをするぞ!と意識した瞬間に、無意識の動きとは異なってきます。
あれ~?となり、どんどん混乱していくような形になります。笑
ですが、この時に、なんとなくでも『グッとしてシュって感じ』みたいな自分自身の中で、再現できる感覚があるなら、文字通り【再現できるんです】。
例えば、力を込める自分自身の感覚を5段階に分けて、強い方から①、②、③、④、⑤とします。(⑤が一番力を抜いている)
そして、結果(パフォーマンス)が良かった順に、A、B、C、D、Eとします。(Eが一番結果が良くなかった)
実はこの時、①=A、②=B、③=C、④=D、⑤=E とはならずに、
①=E、②=D、③=B、④=A、⑤=C のように順序が入れ替わったりします。
①、②、③、④、⑤ と自分自身で把握していて、しっかりとコントロールできていれば、
再現することは難しくないし、その時の結果によって調整も出来るようになります。
ですが、①~⑤の感覚がバラバラだったり、わかっていなかったら…
動作分析を行って、動きに合わせてしまうと感覚が狂ってしまって、どんどんドツボにはまっていってしまう危険性があるんです。
- 身体感覚を伸ばすためには、違いを感じること
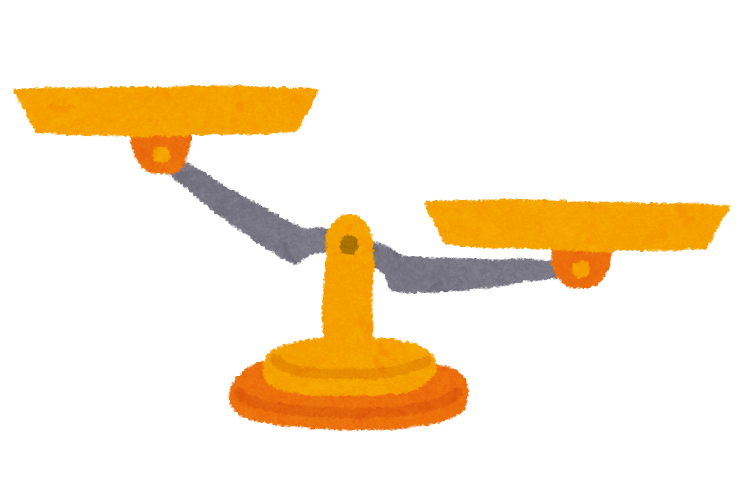
動作分析を確実に結果に繋げるためには、自分自身の体の感覚を掴むことが必要不可欠です。
体がどのような状態にあるのかを正確に感じ取る『身体感覚』と
体を思い通りに動かせるようための『身体操作』はセットになります。
『身体操作』は練習やトレーニングをしていけば伸ばせる、というのは想像に難くないと思います。
『身体感覚』と言われると、感覚だけにどうして伸ばしたらいいんだ?と感じてしまうのではないかと思います。
ですが、実際には『身体感覚』も練習を積み重ねていけば、伸ばせるようになるんです。
その『身体感覚』を伸ばす方法とは、
動きの違いを感じ取ること。
先ほどの、①~⑤までの感覚、はじめはわからなくてもいいので、なんとなくでも5段階に分けるようにしていきます。①から順番に⑤まで徐々に力を抜いていくようにします。
慣れてきたら今度は⑤から①に徐々に力を込めていきます。
次は、ランダムで再現できるようにしていく・・・
というようなことをしていると、①~⑤のそれぞれの違いを感じ取ることができるようになってきます。
それと同時にコントロールも出来るようになってくるのです。
生まれつき、運動神経が良いと言われる人は、『身体操作』の能力が高い人が多いです。
競技の練習をしていけば自然と『身体操作』は伸ばせます。
ですが、そこから大成して、プロの世界でも飛びぬけられる人というのは『身体感覚』の能力も高かったりもします。
『身体感覚』の方はなかなか伸ばそうという人が少ないです。
自分の体は思い通りに動いている、と思い込んでしまっている人が多いからかなぁ…とは思うのですが。。。
あと、上記の『身体感覚』を伸ばすための練習が地味すぎて、継続できない人が多いということもあったりします。
「そんなことをしているよりも競技の練習をした方がうまくなれるでしょ!」
と実際に、京都大学に指導に行ってる時に選手にも言われた言葉です。
まぁ競技の練習だけでは頭打ちになってるから、監督さんがこういったトレーニングを取り入れられてるんですけどね…
それを理解できる人も少ないよなぁ…とは思います。
- いかに面白く、楽しく伝わるか

理解できる人が少ないから、といって諦めても良いものでもなくて、どうすれば伝わるのか?理解してもらえるのか?を試行錯誤するのが私の仕事だとも思っています。
だって、これが理解できれば、パフォーマンスが上がるのは間違いないのだから。
そういった今までの経験も含めて、今回の京都両洋高校のサッカー部の講習会では、自分の体に意識を向けてもらうことにもらっています。
特に、「ちょっとした意識の違いで、感覚がかなり変わるんだ!」ということを感じてもらい、
体の使い方の楽しさや面白さを体感していただけるように工夫しています。
今すぐに結果に結びつく、というものではないですが、『身体感覚』が伸びれば、それ以上に上達スピードは上がります。
徐々にかもしれませんが、『身体感覚』、『身体操作』について認知が広がっていけば良いなと思っています。
そうすれば、痛みで悩む人は減らせるでしょうし、スポーツのパフォーマンスも高められますからね!