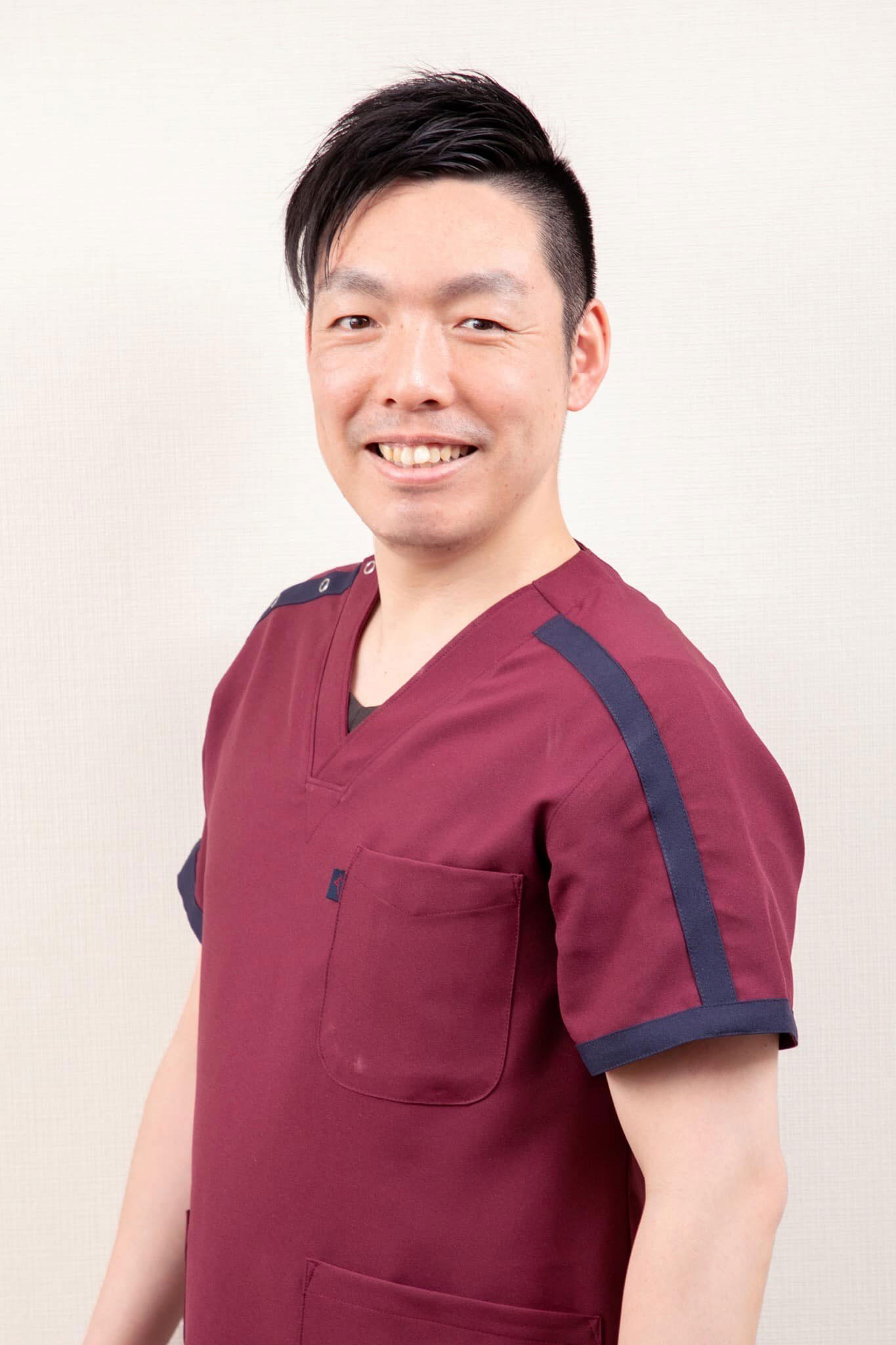【決定版】五十肩の治療最前線!「自分の身体は自分で治せる」が基本方針の二つの国家資格(柔道整復師、鍼灸師)を持つ専門家が徹底解説

「まさか、私が五十肩になるなんて…」そんなふうに思っていませんか?
当院に来院される五十肩の患者様も、最初は同じようなことをおっしゃいます。
「突然、肩に違和感を覚えるようになりました…」
「最初は『ちょっと肩が凝っただけかな?』と軽く考えていましたが、日が経つにつれて痛みは増すばかり。腕を上げようとすると、ズキーンと激痛が走り、夜も眠れないほど痛むようになりました」
「服を着るのも、髪を洗うのも、一苦労。ちょっとした動作でも激痛が走る…」
「洗濯物を干すのも、高いところにある物を取るのも、腕が上がらないから諦めるしかない…」
「夜中に痛くて目が覚めてしまい、熟睡できない。常に疲労感が抜けない…」
「車の運転も、バックするのが怖い。肩が回らないから、後ろが見えないんです…」
「趣味のガーデニングも、腕が痛くてできなくなってしまった。楽しみが減ってしまった…」
五十肩は誰にでも起こりうる病気であり、日常生活にも大きな影響を与えます。
しかし、適切な治療を受けることで、症状を改善し、快適な生活を取り戻すことができます。
この記事では、五十肩の原因、症状、治療法について、現場を知る鍼灸師が徹底的に解説します。
目次
⒈ 五十肩とは?痛くて腕が上がらない!原因と症状をチェック!

「肩が痛くて腕が上がらない…」「夜中に肩の痛みで目が覚める…」
もしかして、それは五十肩かもしれません。
五十肩は、40代~60代に多くみられる肩の痛みで、正式には「肩関節周囲炎」といいます。
肩こりと混同されがちですが、五十肩は肩の痛みだけでなく、腕が上がらない、後ろに回せないといった可動域制限を伴うのが特徴です。
(1) 五十肩の症状をチェック!
これらの症状に複数当てはまる場合は、五十肩の可能性があります。
・肩の痛み(ズキズキ、刺すような、重苦しいなど)
・腕を上げるときの痛み
・腕を後ろに回すときの痛み
・夜間痛(寝ているときに痛む)
・肩の可動域制限(腕が上がらない、後ろに回せないなど)
(2) 五十肩の原因って?
五十肩の原因は、実はまだはっきりわかっていません。
しかし、加齢による腱板(肩関節を動かす筋肉)の変性や、肩関節周囲の炎症などが関与していると考えられています。また、猫背などの姿勢不良、運動不足、冷え性、ストレスなどの要因も、五十肩のリスクを高める可能性があります。
(3) 五十肩を放置するとどうなる?
五十肩を放置すると、痛みが慢性化したり、可動域制限が残ったりする可能性があります。
また、日常生活にも支障をきたし、QOL(生活の質)が低下する原因にもなります。
「もしかして五十肩かも?」と思ったら、専門家に相談しましょう。
⒉ 一人の治療家が柔道整復師と鍼灸師という国家資格者を所持!だから五十肩の改善が効果的!

一人の治療家が柔道整復師と鍼灸師の両方の国家資格を所持していることは、五十肩(肩関節周囲炎)の改善において非常に効果的なメリットをもたらします。それぞれの専門性を活かした多角的なアプローチが可能になるため、より根本的な原因に迫り、症状の緩和だけでなく、可動域の改善や再発予防にも繋がりやすくなります。
(1) 具体的なメリット
① 構造的な問題と機能的な問題の両面からの評価とアプローチ
柔道整復師の視点:肩関節の可動域制限、周囲の筋肉(ローテーターカフ、三角筋など)の拘縮や炎症、肩甲骨の動きの悪さ、姿勢不良など、五十肩に関わる構造的な問題を評価し、手技療法(マッサージ、整体、関節モビライゼーションなど)や運動療法によって改善を試みます。
鍼灸師の視点:肩関節周囲の経絡の滞り、気血の流れの悪化、炎症、痛みを引き起こす可能性のある全身のアンバランスなどを東洋医学的な観点から評価し、鍼やお灸を用いてこれらの問題にアプローチします。
両方の視点を持つことで、五十肩の痛みの原因や可動域制限の要因をより深く理解し、多角的な治療戦略を立てることができます。 例えば、肩関節の癒着だけでなく、全身の血行不良や冷えが症状を悪化させている場合などに対応できます。
② 多様な治療法の組み合わせによる相乗効果
手技療法で肩関節周囲の筋肉の緊張を緩め、関節の動きを改善した後に、鍼灸治療でさらに深部の組織や神経、血流にアプローチすることで、より高い鎮痛効果や可動域改善効果が期待できます。
鍼灸治療で炎症を抑えたり、痛みを緩和したりすることで、運動療法を行いやすくなり、より効果的なリハビリテーションを進めることができます。
患者さんのその日の状態や症状に合わせて、最適な治療法を柔軟に選択・組み合わせることができるため、よりパーソナルな治療を提供できます。
③ 痛みの緩和と可動域改善への効果的なアプローチ
柔道整復術:関節の動きを滑らかにするための手技や、拘縮した筋肉を緩めるためのアプローチ、適切な運動指導により、痛み軽減と可動域の改善を直接的に促します。
鍼灸治療:痛みを伝える神経経路を遮断したり、炎症を抑える物質の放出を促したりすることで、鎮痛効果を発揮します。また、血行促進作用により、組織の修復を促し、可動域の改善をサポートします。
④ 原因の特定と根本的な改善への期待
五十肩は、加齢による組織の変性だけでなく、姿勢不良、肩の使いすぎ、血行不良、ストレスなど様々な要因が複合的に関わっている場合があります。両方の資格を持つ治療家は、これらの要因を多角的に評価し、より根本的な改善を目指した治療を行うことができます。
⑤ 再発予防への取り組み
痛みが軽減し、可動域が改善した後も、柔道整復師の視点から適切な姿勢指導や運動療法、鍼灸師の視点から体質改善や全身のバランス調整を行うことで、五十肩の再発予防に繋げることができます。
⑥ スムーズな連携と効率的な治療
異なる治療法を受けるために複数の医療機関を受診する必要がなく、一人の治療家が一貫して対応できるため、時間や手間を省くことができます。治療方針の変更や調整もスムーズに行うことができ、患者さんの状態に合わせて臨機応変に対応できます。
⑦ 患者さんとの信頼関係の構築
多様な治療法を提供できることで、患者さんの様々なニーズに応えることができ、信頼関係を築きやすくなります。一人の治療家が責任を持って最初から最後まで対応することで、患者さんは安心して治療を受けることができます。
このように、一人の治療家が柔道整復師と鍼灸師の両方の資格を持つことは、五十肩の複雑な病態に対して、より包括的で効果的なアプローチを可能にするため、改善が期待できると言えます。ただし、治療家の知識や技術レベルによって効果は異なりますので、信頼できる治療家を選ぶことが重要です。
⒊ 現場を知り尽くした2つの国家資格を持つ専門家の五十肩治療のポイント

現場を知り尽くした柔道整復師と鍼灸師という2つの国家資格を持つ専門家の五十肩治療のポイントは、それぞれの専門性を深く理解し、臨床経験に基づいて患者さんの状態を的確に把握し、最適な治療法を組み合わせることにあります。以下に、具体的なポイントを挙げます。
(1) 徹底的な問診と評価による原因の特定
① 柔道整復師としての評価
肩関節の可動域(屈曲、外転、外旋、内旋など)の制限の程度とパターンを詳細に把握します。痛みの部位、種類、誘発動作、時間経過などを詳しく聞き取り、炎症の程度や組織損傷の可能性を評価します。
姿勢、肩甲骨の動き、頚椎の状態など、肩関節に影響を与える全身の構造的な歪みをチェックします。
棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋(ローテーターカフ)をはじめとする肩関節周囲筋の筋力、柔軟性、圧痛などを評価します。
② 鍼灸師としての評価
痛みの性質(ズキズキする、重い、鈍いなど)、時間帯による変化、温めると楽になるか冷やすと楽になるかなどを東洋医学的に分析します。
全身の倦怠感、冷え、のぼせ、消化器系の不調など、全身状態と五十肩との関連性を探ります。
③ 両方の視点からの統合
これらの情報を総合的に判断し、五十肩の直接的な原因(関節包の癒着、腱板の炎症など)だけでなく、それを引き起こしている可能性のある根本的な要因(姿勢不良、使いすぎ、血行不良、内臓の機能低下、ストレスなど)を探ります。
(2) 病期に合わせた適切な治療戦略
① 急性期(炎症が強い時期)
柔道整復師:無理な運動や強い刺激は避け、痛くない範囲で体を動かすことや、しっかりと水を飲むことも推奨しています。痛みの少ない範囲での可動域維持訓練や、周囲の筋肉の緊張緩和を目的とした軽いマッサージなどを行います。
鍼灸師:炎症を鎮め、痛みを緩和するツボ(合谷、曲池など)への刺激の鍼治療や、炎症を抑える効果のある灸治療(間接灸など)を行います。全身の気血の流れを整え、自然治癒力を高める治療も行います。
② 慢性期(拘縮が主な時期)
柔道整復師:手技療法と運動療法(ワーク)で、徐々に関節の可動域を広げるためのストレッチやモビライゼーション、運動療法(コッドマン体操、壁を使った運動など)を段階的に指導します。肩甲骨の動きを改善するアプローチや、姿勢改善の指導も重要になります。
鍼灸師:拘縮した組織の血行を促進し、柔軟性を取り戻すためのツボ(肩髎、肩ぐうなど)への鍼治療や温灸を行います。全身のエネルギーの流れを改善し、組織の修復を促す治療も行います。
③ 回復期(可動域が改善してきた時期)
柔道整復師:再発予防のための筋力トレーニングや、日常生活動作における注意点などを指導します。より実践的な動作を取り入れた運動療法を行い、肩関節の安定性を高めます。
鍼灸師:全身のバランスを整え、体質改善を促す治療を継続することで、再発しにくい体づくりをサポートします。必要に応じて、肩関節周囲の筋肉の柔軟性維持や血行促進を目的としたメンテナンス治療を行います。
(1) 双方の技術を活かした効果的な手技と鍼灸の組み合わせ
例1: 柔道整復の手技で肩関節周囲の筋肉の緊張を緩め、関節の動きをある程度改善させた後に、鍼治療で深部の組織や神経にアプローチし、より高い鎮痛効果や可動域改善効果を引き出す。
例2: 鍼灸治療で炎症や痛みを緩和させた状態で、運動療法を行うことで、よりスムーズに可動域を広げ、筋力強化を進める。
例3: 姿勢の歪みが肩に負担をかけていると判断した場合、柔道整復の骨盤矯正や姿勢指導を行いながら、鍼灸治療で全身のバランスを整える。
(2) 患者さんへの丁寧な説明と二人三脚の治療
五十肩の病態、治療の目的と方法、予後などを分かりやすく説明し、患者さんの不安を取り除くことが重要です。
患者さん自身が積極的に治療に参加できるよう、自宅で行えるストレッチや運動療法、日常生活での注意点などを具体的に指導します。治療の経過を共有し、患者さんの声に耳を傾けながら、治療計画を柔軟に修正していきます。
(3) 豊富な臨床経験に基づく応用力
教科書的な知識だけでなく、実際の臨床現場で様々な患者さんの五十肩を治療してきた経験から得られた、独自の治療テクニックやツボの選択、治療のタイミングなどを駆使します。
患者さんの個性や反応を見ながら、臨機応変に治療法を調整する能力が求められます。
これらのポイントを踏まえ、一人の治療家が柔道整復師と鍼灸師の両方の知識と技術を最大限に活かすことで、五十肩の患者さんにとってより効果的で質の高い治療を提供できる可能性が高まります。
⒋ 五十肩の治療に関するQ&A

Q1. 五十肩の治療は、どのくらいで効果が現れますか?
A. 個人差がありますが、効果を実感するだけだと5回以内には実感していただけると思います。患者さんが「改善した、治った」と感じるまでを含めると10~20回くらいは必要な場合もあります。
Q2.鍼灸治療は痛いですか?
A. 鍼を刺す際にチクッとした痛みを感じることがありますが、我慢できないほどの痛みではありません。
⒌ 五十肩の症状改善を目指す

一人ひとり、五十肩の症状や状態は異なります。
適切な治療を受けることで、五十肩の症状を緩和し、生活の質を向上させる効果が期待できます。
そして、より早く効果的に改善に繋げるためには、治療院に通って施術を受けるだけでなく、あなた自身で改善できるような取り組みを行ってもらうことをお勧めします。
ご自宅でも取り組んでいただくことで、施術を受けるだけ、よりも効果的に早期回復・再発予防も目指すことができます。
もしあなたが根本的な解決を望まれてるのであれば、治し方を教えてもらえる治療院を選ぶことも大切です。